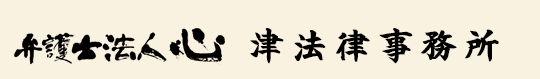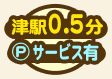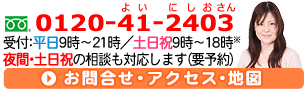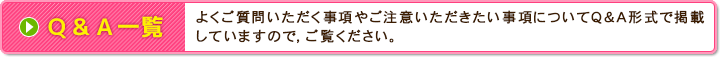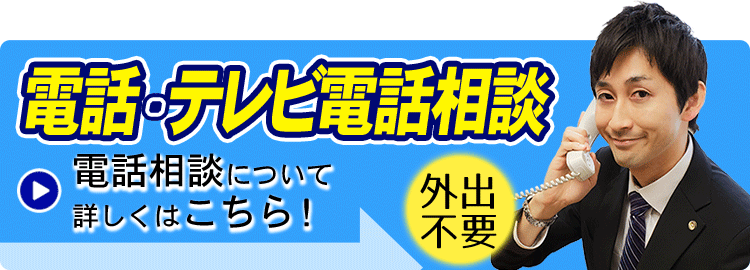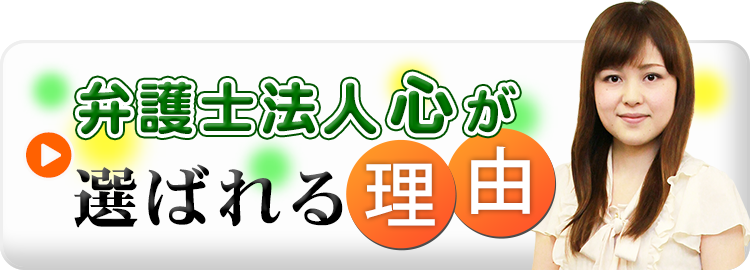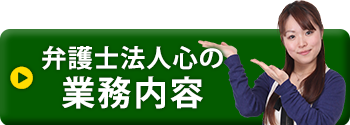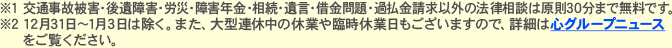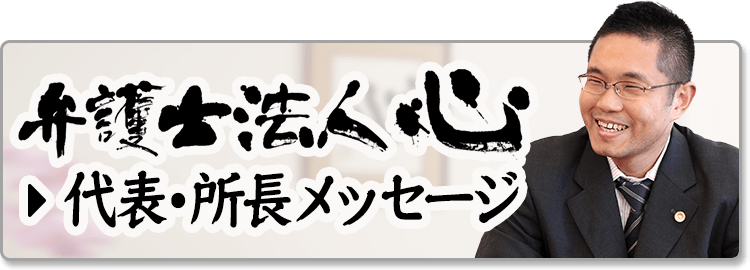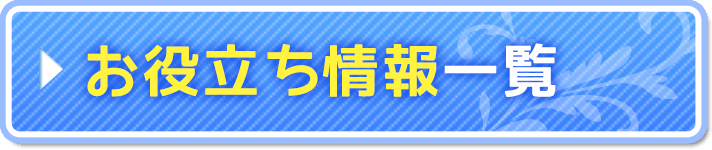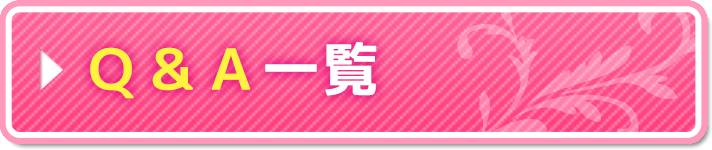障害年金が受給できる年齢
1 初診日に20歳前の場合
障害年金の基本的な仕組みとして、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診察を受けた日)から原則として1年6か月が経過した日を障害認定日といい、障害認定日時点での障害の状態が法令の定める程度に該当すれば、障害年金を受給することができることになっています。
このような請求の仕方を認定日請求といいます。
なお、障害認定日には例外があり、初診日から1年6か月待たなくても障害年金を受給できる場合があります。
初診日において20歳未満であった場合は、上記と異なり、原則として初診日から1年6か月を経過するか20歳になるかのどちらか遅い日が障害認定日となり、それまでは障害年金を受給することはできません。
ただし、初診日において20歳未満であっても厚生年金に加入している場合は、原則として初診日から1年6か月が経過すれば、障害年金を受け取ることができます。
2 65歳以上の場合
障害認定日時点では障害の状態が重くなかったとしても、請求時点では症状が重くなり、法令の定める程度に該当した場合には、障害年金を受給することができます。
このような請求の仕方を事後重症請求といいます。
しかし、65歳以上になると事後重症請求はすることができず、認定日請求しかできなくなります。
参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
また、認定日請求ができ、障害年金を受け取ることができるようになったとしても、65歳以上の場合は老齢年金を受け取ることができる場合が多く、老齢年金と障害年金は両方を受給することはできません。
その場合は、原則として老齢年金と障害年金の金額の多い方を選択することになるため、障害年金を申請するメリットがあるかどうかを十分に検討する必要があります。
障害年金の受給要件 フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給