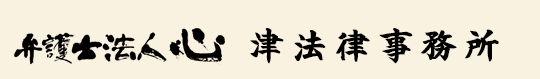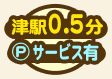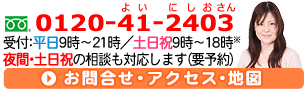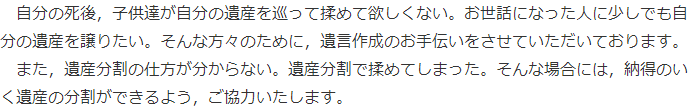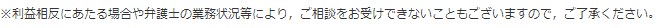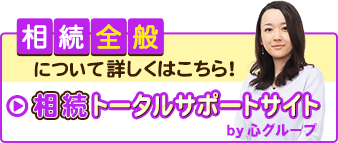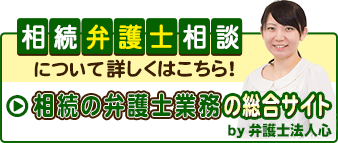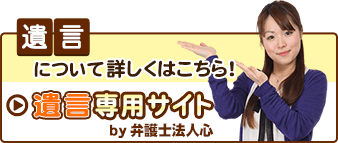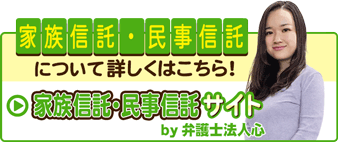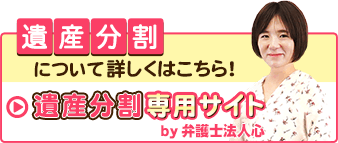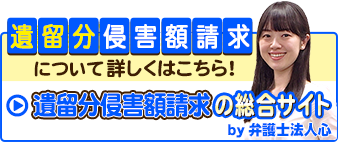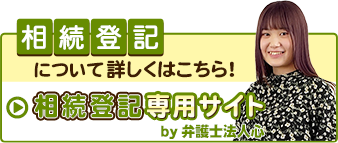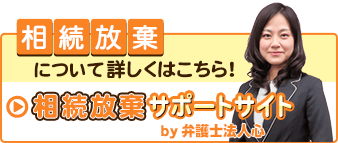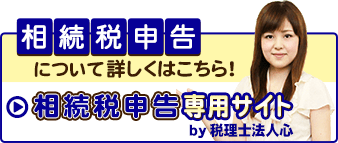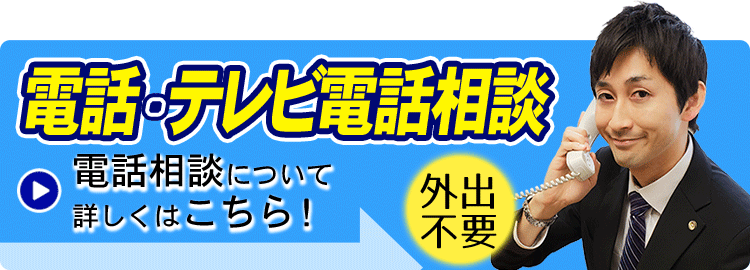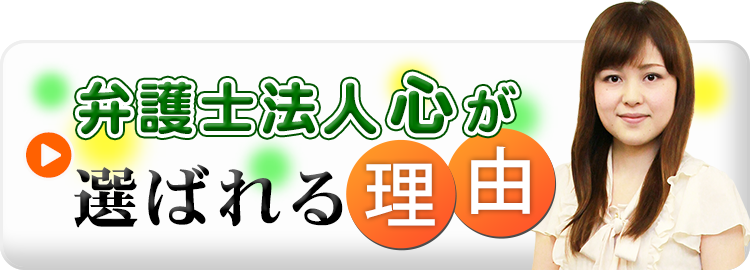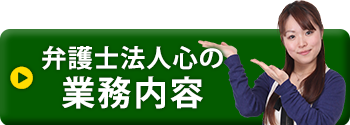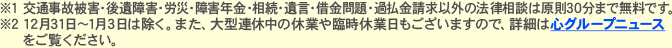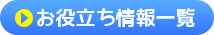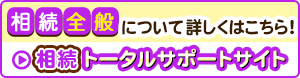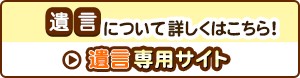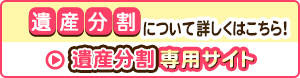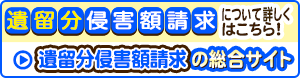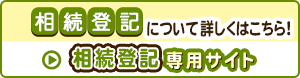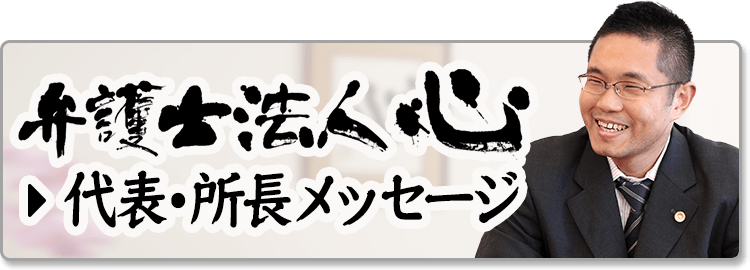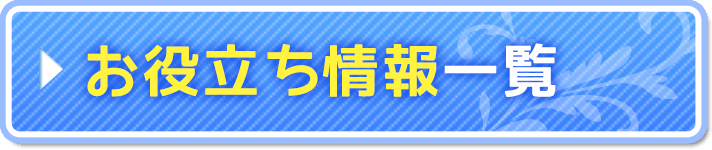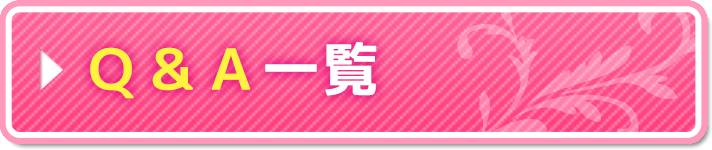相続・遺言
相続に強い弁護士の探し方
1 相続に強い弁護士の条件として考えられること

⑴ 相続を熟知していること
1つ目のポイントは、相続のルールを熟知していることです。
相続には特有のルールが多数存在します。
法律の規定を知っているのはもちろんのこと、過去の裁判所の主要な判断も一通り知っている必要があります。
また、明文化されていない、暗黙のルールのようなものも存在します。
時には、その土地独特のルールが現れることもあります。
こうした独特なルールを知っているかどうかにより、必要な調査を尽くせるかどうか、交渉や裁判を有利かつ円滑に進められるかどうかが、大きく変わってくることもあります。
こうしたルールを熟知している弁護士が、相続に強い弁護士であるということができます。
⑵ 有効性の高い対応策を立てられること
2つ目のポイントは、今後の交渉や裁判を予想し、有効性の高い対応策を立てることができることです。
ルールを知っていても、これらを有効活用できなければ、意味がありません。
そのためには、事案に応じた有効性の高い対応策を立てる必要があります。
その前提として、今後の展開を正確に予想することも必要になってきます。
こうした能力をもっている弁護士は、相続に強いということができます。
2 相続に強い弁護士を探す際のポイント
⑴ 相続の案件を多く扱っている
相続の案件を多く扱っている弁護士は、上述した条件を満たしやすいといえます。
なぜなら、相続の案件を多く扱っていると、相続独特のルールに何度も当たることとなり、出現頻度の低いルールも含めて、ルールを熟知できるようになる可能性が高いです。
また、相続の案件を多く扱っていると、過去の経験から、今後の展開を予想できるようになるといえるからです。
相続の状況は一人一人異なりますし、ご意向も違いますので、それぞれの場合に適した的確なアドバイスをするために、経験やノウハウが活かされるかと思います。
このことから、相続の相談先を探す際は、相続の案件を多く取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
⑵ 実際に相談をしてみて信頼できる弁護士か確認する
次に、実際に相談をしてみて、どのようなアドバイスが得られるかを確認してみることが大切です。
相続を多く取り扱っている事務所であっても、所属している個々の弁護士の能力にはばらつきもあるでしょうし、ただ案件を多く取り扱っているだけで、案件処理自体は杜撰であるという弁護士もいないわけではないと思います。
したがって、実際に相談してみて、信頼できる弁護士かどうかを確かめてみることが重要であるといえます。
この点では、複数の弁護士に相談してみて、それぞれの弁護士の回答を比較してみるといったことも、信頼できる弁護士を探す方法としては有効であると考えられます。
弁護士に相続について依頼する場合の費用
1 弁護士に相続について依頼する場面

弁護士に相続について依頼する場面には、様々なものがあります。
もっとも、大別すると、手続きを依頼する場合と、紛争における代理人を依頼する場合に分かれてきます。
それぞれの場面で、弁護士に依頼する費用の決め方も異なってきます。
ここでは、手続きを依頼する場合と紛争における代理人を依頼する場合に分けて、弁護士に依頼する場合の費用を説明したいと思います。
また、現在では、弁護士の費用の定め方は自由化されており、弁護士事務所ごとに費用の定め方はまちまちとなっています。
ここでは、1つの目安として、費用の定め方が自由化される前に用いられていた基準である、日弁連の旧規程を紹介したいと思います。
これは、自由化がなされた現在でも、日弁連の旧規程に基づいて費用を決めている事務所が比較的多いためです。
弁護士に相続について依頼する場合の費用の目安としてご覧いただければと思います。
2 手続きを依頼する場合
弁護士に相続の手続きのみを依頼する場合があります。
相続人間で遺産分割についての意見が一致している場合、有効な遺言が存在している場合には、手続きのみの依頼で完結することとなります。
日弁連の旧規程では、遺言執行費用について、以下のとおり定めていました。
・経済的利益が300万円以下の場合
30万円
・経済的利益が300万円~3000万円の場合
経済的利益の2%+24万円
・経済的利益が3000万円~3億円の場合
経済的利益の1%+54万円
・経済的利益が3億円超の場合
経済的利益の0.5%+204万円
3 紛争における代理人を依頼する場合
遺産分割についての意見がまとまらない場合、弁護士が代理人となり、相手方と交渉したり、裁判手続きを行ったりする場合があります。
また、遺言が存在する場合であっても、遺言の有効性自体が争われたり、遺留分の主張がなされたりする場合があります。
このように、弁護士が紛争における代理人として活動する場合は、民事事件についての基準が用いられます。
日弁連の旧規程では、民事事件の費用について、以下の定めを置いていました。
・経済的利益が300万円以下の場合
着手金:経済的利益の8%
報酬金:経済的利益の16%
・経済的利益が300万円~3000万円の場合
着手金:5%+9万円
報酬金:10%+18万円
・経済的利益が3000万円~3億円の場合
着手金:3%+69万円
報酬金:6%+138万円
・経済的利益が3億円超の場合
着手金:2%+369万円
報酬金:4%+738万円
着手金とは、弁護士が代理人としての活動を開始するにあたり、発生する費用です。
この段階では、経済的利益は、相手方に請求する金額をベースに計算します。
報酬金は、事件の解決時に発生する費用です。
経済的利益については、裁判所が認めた金額や相手方から回収できた金額をベースに計算します。
ただし、日弁連の旧規程は、相続案件では、経済的利益のうち、相続分の範囲内であり、かつ、相続分について争いがない部分については、経済的利益に3分の1を乗じるとの減額調整を行うものとしていました。
4 法律相談の際にしっかりと確認することが重要
上記の日弁連の旧規定は、参考にはなりますが、最終的には依頼を検討している事務所の費用をしっかりと確認することが大切です。
当法人では、ご相談は原則として無料で対応させていただいておりますので、どれくらい費用がかかるのかを知りたいという方もお気軽にご相談ください。
津駅すぐという津市にお住まいの方にはお越しいただきやすい場所に事務所があり、また、電話相談も承りますので、お気軽にご相談いただけます。
相続で弁護士に相談するとよい場合
1 相続で行う様々な手続き

相続では、様々な手続きを行うことになります。
まず、相続人が誰かを特定して、相続財産についての調査を行います。
そして、相続財産の分割方法についての話し合いを行い、誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。
分割方法が決まったあとには、合意内容を書面で明確にしておくべきでしょう。
その後、不動産の登記手続きや預貯金の払戻し手続き、株式や投資信託の換金手続き等を行う必要があります。
また、財産を受け継ぎたくない場合や、一部の相続人に多額の生前贈与があった場合などは、上記以外の手続きを行うこともあります。
このような手続きを行う中でも、特に弁護士に相談した方がよいケースがありますので、以下でご説明します。
2 弁護士に相談した方がよい場合
⑴ 意見の対立がある場合
相続人同士で意見の対立がある場合、もしくは意見の対立が発生する可能性がある場合には、弁護士に相談するべきです。
意見が対立することなく、合意に基づいて相続の手続を進めることができる場合には、法的な問題を検討する必要は少ないといえます。
他方、意見が対立してしまっている場合には、法的にはどのような解決となる可能性が高いのかを検討し、これをベースに話し合い等を行う必要が出てきます。
弁護士は代理交渉が可能ですので、法的な観点から適切な対応を検討し、依頼者の方に代わって交渉いたします。
話し合いでの合意を目指せるように、両者が納得できる落としどころを提案する等の対応もできます。
また、話し合いによる解決が困難な場合は、調停等の手続きを利用することを検討する必要も出てきます。
調停に発展したとしても、弁護士は依頼者の方の代理人として対応できます。
⑵ 疑義のない文書を作成したい場合
また、意見の対立がない場合であっても、合意内容を書面で明確にしなければ、スムーズに相続手続きを進めることはできません。
このような合意内容を記載した書類は、遺産分割協議書と呼ばれます。
遺産分割協議書では、合意内容が一義的に明確に記載されていなければ、その後の手続きを進めることができないおそれがあります。
このように、疑義のない法的文書をきちんと作成する場合には、法律の専門家である弁護士に相談するのが望ましいといえます。