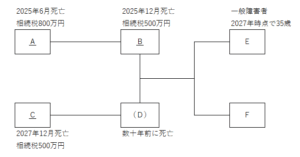1 相続税の課税対象になる不動産の調査方法
相続税の課税対象になる不動産は、毎年の4月から5月にかけて届く固定資産納税通知書か、市町村役場で取得できる名寄帳で確認することができます。
これらの書類には、ある市町村において、被相続人が所有していた不動産の一覧が記載されています。
ところで、固定資産納税通知書や名寄帳で不動産を調査する際には、何点か注意しなければならないことがあります。
具体的には、以下のとおりです。
2 その年の1月1日時点の所有不動産が記載されていること
固定資産納税通知書や名寄帳には、その年の1月1日時点の所有不動産が記載されています。
このため、その年の1月1日以降、不動産を取得したり、不動産を売却したりしており、不動産の名義が変更されている場合、固定資産納税通知書や名寄帳では、こうした変更は反映されていないこととなります。
その年の1月1日以降、不動産の名義変更が行われている場合は、登記簿を確認し、不動産の現在の所有者を確認する必要があります。
3 単独所有の不動産と共有の不動産が別々に記載されていること
市町村の台帳では、単独所有の不動産と共有の不動産は別々に記載されています。
このため、固定資産納税通知書については、単独所有の不動産と共有の不動産とで、別々に届くこととなります。
また、名寄帳も、単独所有の不動産と共有の不動産とで別々に作成されることとなります。
このため、不動産を調査するにあたっては、単独所有の不動産だけでなく、共有の不動産も見逃さないようにしなければなりません。
4 先代名義の不動産が存在する可能性があること
先代名義の不動産が、名義変更されることなく、そのまま残っていることがあります。
こうした不動産についても、被相続人は、相続分に相当する権利を有していたものと評価されますので、不動産の相続分相当額について、相続税申告の対象にする必要があります。
ところが、市町村の台帳では、被相続人名義の不動産と先代名義の不動産は別々に記載されています。
このため、先代名義の不動産の存在が認識されることなく、申告漏れになってしまうことがしばしばあります。
相続税申告の際には、こうした先代名義の不動産についても、共有の不動産と同様、見逃さないように注意する必要があります。
※三重県でも、このような不動産の存在が後で明らかになることが多いですので、意識して調査を進める必要があります。